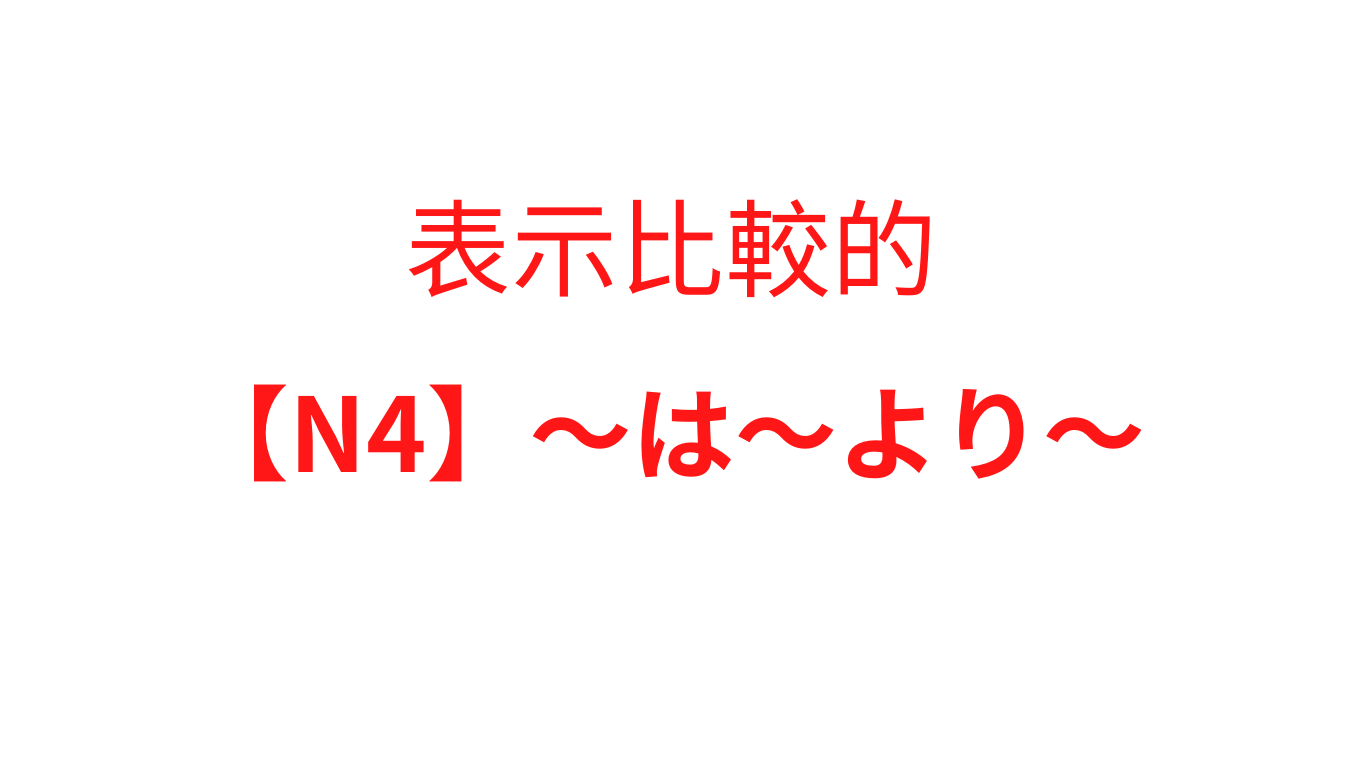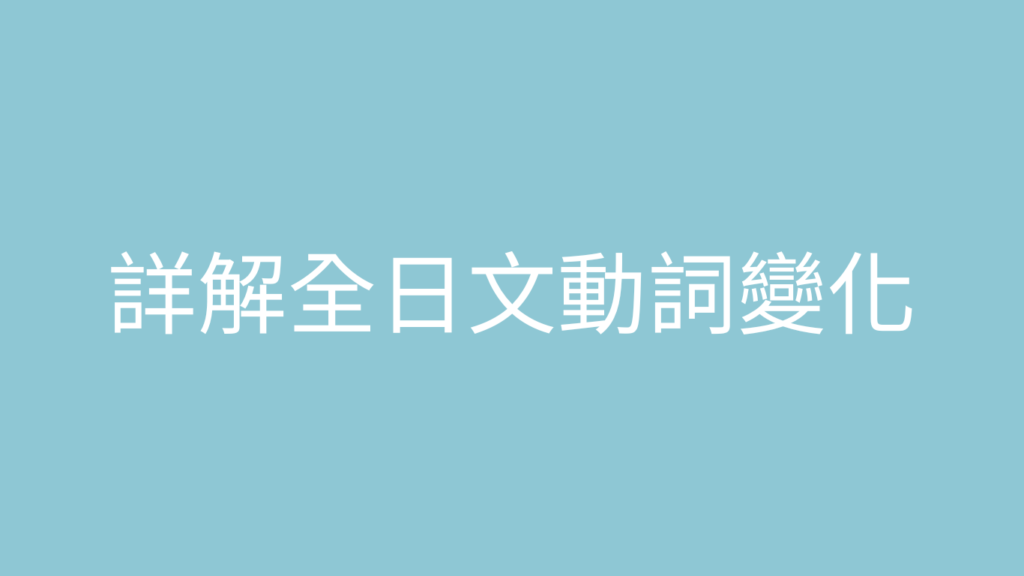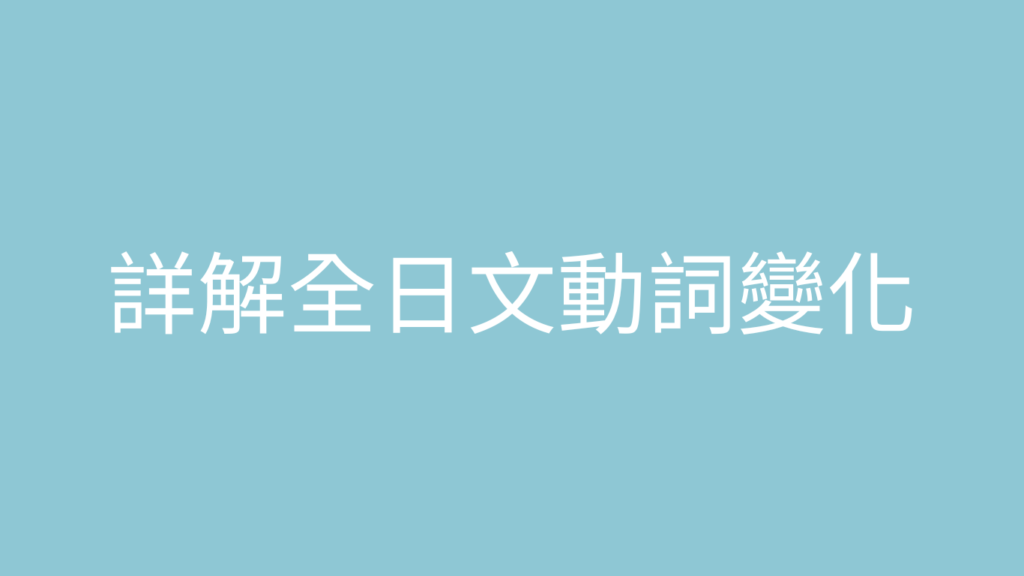
學動詞變化時,需要注重2點:
1・什麼體系的動詞?(基本体?還是敬体?)
2・動詞第幾類?(辞書形可以迅速分辨,但ます形很難)
※基本体又可以稱為「普通体」或是「常体」、「普通形」,依照老師、課本的不同,稱法也會不一樣,不過都是同一個東西。
在這一篇裡,我會用「以外國人為對象的動詞教學方式」來講解,並不會用「日本人的動詞學習系統」來教大家。
OK老師本身就是日本籍,兩個教法都知道,其實日本人在國中時就有學過「日本人的動詞學習系統」,其實這完完全全就是日本人教日本人的東西。
「日本人的動詞學習系統」的正式名稱為「学校文法」,這個呢,我覺得用「學校文法」來說明的話,對大家來說太過於複雜,而且太難了。
不過,我擔心看部落格的同學的老師是老一輩的人,課堂上都教「日本人的動詞系統」,所以我還是會放上「日本人的動詞系統」上的動詞類別名稱,讓大家好辨認。
那,在這一篇裡,大家可以學到:
一、動詞分類
動詞分三類。
分別有第一類、第二類、第三類。
(但在學校文法裡分五類,分別是「五段動詞」、「上一段動詞」、「下一段動詞」、「カ行変格動詞」、「サ行変格動詞」)
我們在分類時先以「辞書形」來做分類吧。
第一類 (又稱為五段動詞):除了第二類和第三類的動詞以外。如果後面連「る」都沒有的一定是第一類。如,「飲む」、「折る」、「取る」、「笑う」等。
第二類 (又稱為上一段、下一段動詞):只有「iる」和「eる」的動詞。如,「起きる」和「食べる」、「止める」等。
第三類 (又稱為カ行変格動詞、サ行変格動詞):只有兩個動詞,「する」和「来る」,死背就好。
接下來,請試著把動詞分類看看。
1・読む
2・寝る
3・下げる
4・いる
5・連絡する
6・喜ぶ
7・指す
8・来る
9・着る
10・売る
答案是:
1・第一類。最後面是「む」結尾,所以一定是第一類。
2・第二類。後面有「る」,「る」的前面是「ね(ne)」,符合第二類的標準。
3・第二類。後面有「る」,「る」的前面是「げ(ge)」,符合第二類的標準。
4・第二類。後面有「る」,「る」的前面是「い(i)」,符合第二類的標準。
5・第三類。只要看到「する」就是第三類,不需要管「する」前面是什麼。
6・第一類。最後面是「ぶ」,所以一定是第一類。
7・第一類。最後面是「す」,所以一定是第一類。
8・第三類。只要看到「来る」就是第三類。
9・第二類。後面有「る」,「る」的前面是「き(ki)」,符合第二類的標準。
10・第一類。後面雖有「る」,但「る」的前面是「う」,沒有「i」或是「e」的音,不符合第二類,所以就是第一類。
注意點:
1・你沒有看過的動詞,可以以「辞書形」去做分類,但「敬体」或是「ます形」時,你是沒辦法直覺性的去分類的。因為「ます」前的音,不管是第一類或是第二類都有「i」的音,容易混淆。
2・要記動詞時,一定也要一起記第幾類。
例外:
有些動詞像是「切(ki)る」,看起來明明就是第二類,但卻是第一類..這種動詞還蠻多的,但其實說多也不多。所以我把例外動詞全部都寫上去,之後看到例外就可以應付了。
要る:第一類動詞
選る:第一類動詞 (日本人不常用動詞,所以大家應該幾乎不會看到)
切る:第一類動詞
蹴る:第一類動詞
知る:第一類動詞
競る:第一類動詞 (日本人不常用動詞,所以大家應該幾乎不會看到)
散る:第一類動詞
照る:第一類動詞 (日本人不常用動詞,所以大家應該幾乎不會看到)
練る:第一類動詞
減る:第一類動詞
二、て形、た形
其實「て形」和「た形」基本上變法是同一種,只是用法、意思不同而已。
這個「て形」,它本身的意思有很多,如時間的順序、東西事情的並列等,最重要的就是「て形」的功能就是可以幫你連接句子和句子喔。非常好用的一個東西。
不過這一篇文章注重動詞變化,所以更詳細的內容,我會另外再寫一篇內容。
「た形」呢,最基本的就是使用在「基本体的過去式」上,其他還有很多可以接「た形」,像是「た形+ほうがいい」表示建議「我建議你做~比較好」,更詳細的內容之後再說吧。
接下來,我們來試著把「辞書形」改成「て形」吧。
第一類動詞:
尾巴有「う」、「つ」、「る」的動詞,請改為「って」。
尾巴有「ぶ」、「む」、「ぬ」的動詞,請改為「んで」。
尾巴有「す」的動詞,請改為「して」。
尾巴有「く」的動詞,請改為「いて」。
尾巴有「ぐ」的動詞,請改為「いで」。
第二類動詞:
所有第二類動詞的尾巴「る」,直接改為「て」就可以了。
第三類動詞:
「する」改為「して」
「来る」改為「来て」
試試看:
1・取る
2・書く
3・間違える
4・読む
5・騒ぐ
答案:
1・第一類動詞,所以「る」改「って」,答案就是「取って」
2・第一類動詞,所以「く」改「いて」,答案就是「書いて」
3・第二類動詞,所以「る」改「て」,答案就是「間違えて」
4・第一類動詞,所以「む」改「んで」,答案就是「読んで」
5・第一類動詞,所以「ぐ」改「いで」,答案就是「騒いで」
接下來我們一起來看「た形」。
其實和「て形」的變化是一模一樣的,只是最後的「て」改「た」而已。
1・取る→取って→取った
2・書く→書いて→書いた
3・間違える→間違えて→間違えた
4・読む→読んで→読んだ
5・騒ぐ→騒いで→騒いだ
注意點:
1・「て形」如果有濁音,那換成「た形」時也要有濁音。如,「呼ぶ」→「呼んで」→「呼んだ」。
2・唯一一個例外就是「行く」,它的て形是「行って」,た形就是「行った」。
三、「敬体」的時態變化
「敬体」又稱為「丁寧体」或是「禮貌体」。
在學日文時,一開始一定先從「敬体」開始學,因為動詞不需分類,變化也不多,而且又簡單好上手。
「敬体」就是一個要區分時態的大體系,而且是有禮貌的時態 (所以才稱為「敬体」),可以對不認識的人、不是很熟的人、店家,或是工作上使用。
在這裡呢,我們就全程使用「ます形」的動詞去改時態,不使用「辞書形」。
在第四大題的「ます形」會教你如何把「辞書形」改成「ます形」。
以「飲みます」來舉例:
1・現在肯定:飲みます
2・現在否定:飲みません
3・過去肯定:飲みました
4・過去否定:飲みませんでした
不管是第幾類的動詞,「ます」前的東西都不要改,直接改「ます」的部分就可以了。
現在肯定就是「~ます」,現在否定就是「~ません」,過去肯定就是「~ました」,過去否定就是「~ませんでした」。
試試看:
1・食べます
2・拭きます
3・寝ます
4・描きます
5・来ます
答案:
1・現在肯定:食べます。現在否定:食べません。過去肯定:食べました。過去否定:食べませんでした。
2.現在肯定:拭きます。現在否定:拭きません。過去肯定:拭きました。過去否定:拭きませんでした。
3・現在肯定:寝ます。現在否定:寝ません。過去肯定:寝ました。過去否定:寝ませんでした。
4・現在肯定:描きます。現在否定:描きません。過去肯定:描きました。過去否定:描きませんでした。
5・現在肯定:来ます。現在否定:来ません。過去肯定:来ました。過去否定:来ませんでした。
四、ます形
在這邊會教大家如何把「辞書形」換成「ます形」。
首先一定要先分類動詞,再改成「ます形」。
第一類:「u」→「i」+ます
第二類:「る」→「ます」
第三類:「する」→「します」、「来る」→「来ます」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「i」的音再加上ます。
如,「のむ (mu) 」→「のみ (mi) ます」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳上一格音,那就是「み (mi) 」,也可以就是子音不要改,改「i」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「mi」再加上「ます」就好了,所以就是「のみます」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「ます」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべます」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「します」。「くる」→「きます」。
順序:
①先將動詞分類(如果不會,請回到第一大題看)。
②如果是第一類,換最尾巴的音。第二類把「る」改「ます」。第三類整個換掉。
在這裡,一定有人想問「換成ます形要做什麼」。
換成「ます形」就是你今天要改成「敬体」時需要的,而「敬体」就是一個禮貌的時態總稱,可以對不認識的人,或是店家、不是很熟的人,甚至是工作上都會用到。
除了換成「敬体」之後,還有非常多的文法、句型要接「ます形」喔。
像是「ます形+ながら」就是表示「一邊做~一邊做~」的意思。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来ます」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「ます形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
試試看:
1・見る
2・踊る
3・着く
4・泊まる
5・削る
答案:
1・第二類,見ます。
2・第一類,踊ります。
3・第一類,着きます。
4・第一類,泊まります。
5・第一類,削ります。
五、否定形
一樣先將動詞分類,再從「辞書形」改成「否定形」。
第一類:「u」→「a」+ない
第二類:「る」→「ない」
第三類:「する」→「しない」、「来る」→「来ない」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「a」的音再加上ない。
如,「のむ (mu) 」→「のま (ma) ない」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳上兩格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「a」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「ma」再加上「ない」就好了,所以就是「のまない」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「ない」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべない」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「しない」。「くる」→「こない」。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来ない」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「否定形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
3・否定形的第一類的「あ」段音,需改成「わ」的音。如,「あう」→「あわない」(「ああない」是錯誤的。)
試試看:
1・買う
2・貯まる
3・登録する
4・勝つ
5・負ける
答案:
1・第一類,買わない。
2・第一類,貯まらない。
3・第三類,登録しない。
4・第一類,勝たない。
5・第二類,負けない。
六、受身形
「受身形」又稱為「被動形」,一樣先分類動詞,再從「辞書形」改為「受身形」。
第一類:「u」→「a」+れる
第二類:「る」→「られる」
第三類:「する」→「される」、「来る」→「来られる」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「a」的音再加上「れる」。
如,「のむ (mu) 」→「のま (ma) れる」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳上兩格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「a」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「ma」再加上「れる」就好了,所以就是「のまれる」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「られる」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべられる」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「される」。「くる」→「こられる」。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来られる」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「受身形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
3・否定形的第一類的「あ」段音,需改成「わ」的音。如,「あう」→「あわれる」(「ああれる」是錯誤的。)
試試看:
1・話す
2・舐める
3・触る
4・止める
5・起こす
答案:
1・第一類,話される。
2・第二類,舐められる。
3・第一類,触られる。
4・第二類,止められる。
5・第一類,起こされる。
七、使役形
一樣先分類動詞,再從「辞書形」改為「使役形」。
第一類:「u」→「a」+せる
第二類:「る」→「させる」
第三類:「する」→「させる」、「来る」→「来させる」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「a」的音再加上「せる」。
如,「のむ (mu) 」→「のま (ma) せる」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳上兩格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「a」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「ma」再加上「せる」就好了,所以就是「のませる」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「させる」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべさせる」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「させる」。「くる」→「こさせる」。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来させる」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「受身形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
3・否定形的第一類的「あ」段音,需改成「わ」的音。如,「あう」→「あわせる」(「ああせる」是錯誤的。)
試試看:
1・話す
2・舐める
3・触る
4・止める
5・起こす
答案:
1・第一類,話させる。
2・第二類,舐めさせる。
3・第一類,触らせる。
4・第二類,止めさせる。
5・第一類,起こさせる。
八、使役受身形
「使役受身形」又稱為「使役被動形」,一樣先分類動詞,再從「辞書形」改為「使役受身形」。
第一類:「u」→「a」+せられる
第二類:「る」→「させられる」
第三類:「する」→「させられる」、「来る」→「来させられる」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「a」的音再加上「せられる」。
如,「のむ (mu) 」→「のま (ma) せられる」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳上兩格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「a」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「ma」再加上「せられる」就好了,所以就是「のませられる」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「させられる」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべさせられる」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「させられる」。「くる」→「こさせられる」。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来させられる」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「使役受身形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
3・否定形的第一類的「あ」段音,需改成「わ」的音。如,「あう」→「あわせられる」(「ああせられる」是錯誤的。)
試試看:
1・話す
2・舐める
3・触る
4・止める
5・起こす
答案:
1・第一類,話させられる 。
2・第二類,舐めさせられる。
3・第一類,触らせられる 。
4・第二類,止めさせられる。
5・第一類,起こさせられる。
九、辞書形
「辞書形」又稱為「字典形」、「原形」,這也是最基本的型態,也是最好區分類別的一個型態。
如果你要改其他型態時,基本上都是利用「辞書形」來改,不過也有很多老師會以「ます形」來教大家改成別的動詞型態。
雖然從「辞書形」來學習其他動詞型態很方便,也很簡單,但絕對不可以過度依賴「辞書形」。因為日文學習者的最終目標要非常自由的改變動詞型態,來和日本人進行溝通。
第一類:一定停在「u」的音。如,「のむ」、「わらう」等。
第二類:一定停在「る」。如,「たべる」、「みる」等。
第三類:只有兩個,「する」、「来る」。
十、仮定形
一樣先分類動詞,再從「辞書形」改為「仮定形」。
第一類:「u」→「e」+ば
第二類:「る」→「れば」
第三類:「する」→「すれば」、「来る」→「来れば」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「e」的音再加上「ば」。
如,「のむ (mu) 」→「のめ (me) ば」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳下一格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「e」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「me」再加上「ば」就好了,所以就是「のめば」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「れば」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべれば」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「すれば」。「くる」→「くれば」。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来れば」的時候,念法一樣。
2・雖然從「辞書形」來改成「仮定形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
試試看:
1・話す
2・舐める
3・触る
4・止める
5・起こす
答案:
1・第一類,話せば。
2・第二類,舐めれば。
3・第一類,触れば 。
4・第二類,止めれば。
5・第一類,起こせば。
十一、可能形
一樣先分類動詞,再從「辞書形」改為「可能形」。
第一類:「u」→「e」+る
第二類:「る」→「られる」
第三類:「する」→「できる」、「来る」→「来られる」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「e」的音再加上「る」。
如,「のむ (mu) 」→「のめ (me) る」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳下一格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「e」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「me」再加上「ば」就好了,所以就是「のめる」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「られる」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべられる」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「できる」。「くる」→「こられる」或是「これる」(口語)。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来られる」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「可能形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
3・日本人很常說「これる」,非常口語的說法。
試試看:
1・話す
2・舐める
3・触る
4・止める
5・起こす
答案:
1・第一類,話せる。
2・第二類,舐められる。
3・第一類,触れる。
4・第二類,止められる
5・第一類,起こせる。
十二、命令形
一樣先分類動詞,再從「辞書形」改為「命令形」。
第一類:「u」→「e」
第二類:「る」→「ろ」
第三類:「する」→「しろ」、「来る」→「来い」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「e」就可以了。
如,「のむ (mu) 」→「のめ (me) 」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳下一格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「e」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「me」就好了,所以就是「のめ」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「ろ」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべろ」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「できる」。「くる」→「こられる」或是「これる」(口語)。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来い」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「可能形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
試試看:
1・話す
2・舐める
3・触る
4・止める
5・起こす
答案:
1・第一類,話せ。
2・第二類,舐めろ。
3・第一類,触れ。
4・第二類,止めろ
5・第一類,起こせ。
十三、意向形
「意向形」又稱為「意志形」,一樣先分類動詞,再從「辞書形」改為「意向形」。
第一類:「u」→「o」+う
第二類:「る」→「よう」
第三類:「する」→「しよう」、「来る」→「来よう」
第一類改法:
如果你判斷是第一類的動詞,那麼最後面的音「u」,請改成「o」再加上「う」就可以了。
如,「のむ (mu) 」→「のも (mo)う 」。
「のむ」的尾巴的音是「む (mu) 」,「む」的五十音排序那一行就是「まみむめも」,所以你可以跳下一格音,那就是「ま (ma) 」,也可以就是子音不要改,改「o」的音,剛好「のむ」是「mu」,所以你就換成「mo」就好了,所以就是「のもう」。
第二類改法:
如果你判斷是第二類的動詞,那麼什麼都不用想,請直接把「る」改成「よう」就大功告成了。
如,「たべる」,「る」的前面有「e」,而且不是例外動詞,那就改成「たべよう」就OK。
第三類改法:
第三類只有兩個動詞,無規則可言。只要你判斷是第三類,那就直接改吧。
「する」→「しよう」。「くる」→「こよう」。
注意點:
1・第三類的「来る」改為「来よう」的時候,漢字雖一樣,但念法不同。
2・雖然從「辞書形」來改成「意向形」感覺很簡單,但動詞一定要和它本身的類別一起記,不然你沒辦法從別的型態換成你想要的型態。絕對要記動詞和它本身的類別。
試試看:
1・話す
2・舐める
3・触る
4・止める
5・起こす
答案:
1・第一類,話そう。
2・第二類,舐めよう。
3・第一類,触ろう。
4・第二類,止めよう。
5・第一類,起こそう。
十四、「基本体」的時態變化
「基本体」又稱為「常体」、「普通体」或是「普通形」。
「基本体」就是一個要區分時態的大體系,而且一般對話的時態,可以對很熟的人,或是寫報告,不需要對別人尊敬時可用。
而且「基本体」很難,包含了「辞書形」、「否定形」、「た形」等,非常複雜。
以「飲む」來舉例:
1・現在肯定:飲む(辞書形)
2・現在否定:飲まない(否定形)
3・過去肯定:飲んだ(た形)
4・過去否定:飲まなかった(改成否定形後,最後再把「い」改成「かった」)
這裡一樣要先分類,因為「否定形」和「た形」需要先知道動詞類別才能再改變。
試試看:
1・食べる
2・拭く
3・寝る
4・描く
5・来る
答案:
1・第二類。
現在肯定:食べる(辞書形)
現在否定:食べない(否定形)第二類把「る」改「ない」
現在過去:食べた(た形)第二類把「る」改「て」再改「た」
現在否定:食べなかった(~い改かった)
2・第一類。
現在肯定:拭く(辞書形)
現在否定:拭かない(否定形)第一類「u」→ない
過去肯定:拭いた(た形)第一類「て形」(く→いて),再改為「いた」
過去否定:拭かなかった(否定形的「い」改「なかった」)
3・第二類。
現在肯定:寝る
現在否定:寝ない
過去肯定:寝た
過去否定:寝なかった
4・第一類。
現在肯定:描く
現在否定:描かない
過去肯定:描いた
過去否定:描かなかった
5・第三類。
現在肯定:くる
現在否定:こない
過去肯定:きた
過去否定:こなかった
最後,在學日文動詞變化時,絕對不能太過依賴「辞書形」。
那為什麼這一篇內容都在講「辞書形」?
那是因為「辞書形」分類清楚,所以才先從用「辞書形」來開始。
最終目標一定要自由的、迅速的就可以把所有動詞形式換來換去。像是「否定形」換成「ます形」,或是「意向形」換成「使役形」喔。
學習方式:
1.請你先試著記三個動詞。分別是第一類的「とる」,第二類的「みる」,第三類的「する」。
2・動詞變化規則先抄在手邊,一邊換成所有動詞變化看看。
3・請確認你的變化過後的動詞是否有錯。(你可以留言,我來幫你看看是否正確。或是可以到FB日文學習社團留言請教別人,或是請周遭的有學過日文的人幫你看。)
4・沒問題之後,請把所有動詞變化記熟。可以一天記一個動詞變化。
5・把你知道的動詞都可以隨心所欲的變化,那你就出師了。